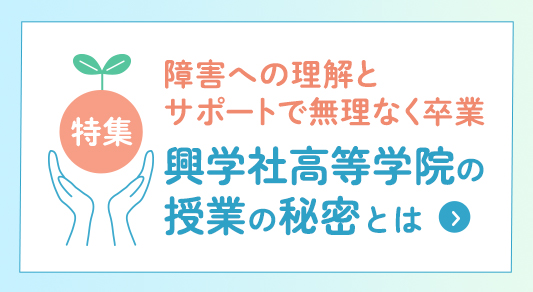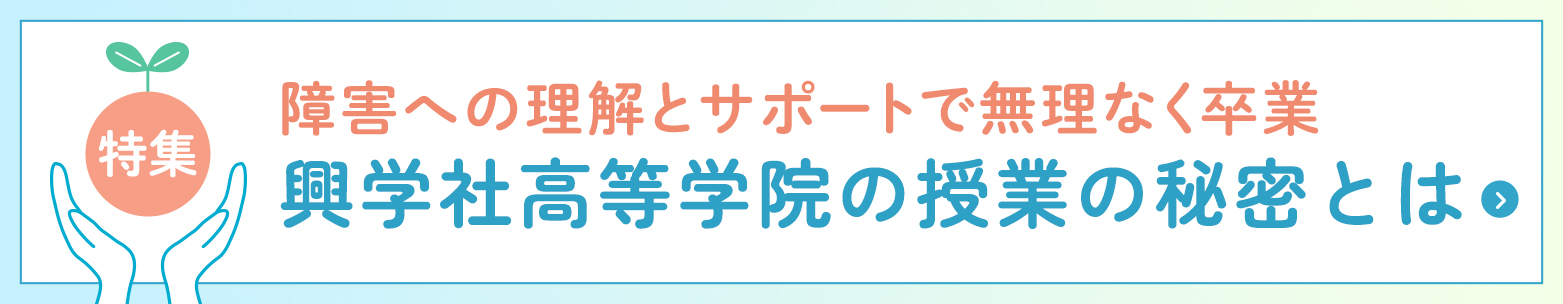「知的障がい」「発達障がい」を抱える子どもの高校受験と進路
発達障がいとは脳機能の発達になんらかの弊害が出ている状態をいい、症状によって様々な種類があります。原因がはっきりとわかっていないものが多く、見た目からはわからないことからも誤解を受けやすく、社会生活を送るのが困難になってしまう事も。
多感な時期でもある高校生活を伸び伸びと過ごし、将来への有意義なステップにするためには、発達障がいそれぞれの特性に合わせた環境の整備やサポートが充実している学校を選ぶ必要があります。ここでは、発達障がいの生徒の高校選びについてご紹介しています。
発達障がいの種類
発達障がいは、広汎性発達障がい・学習障がい(LD)・注意欠陥・多動性障がい(AD/HD)の3つに大きく分けることができます。単に一つの障がいがみられるだけでなく障がいを併存している場合もあり、見た目からは分かりにくいことから診断が難しい面もあります。
また、診断基準を満たしていない場合はグレーゾーンとなり、この場合では周囲からの理解や支援が受けにくくなり、社会生活を送るうえで困難になってしまうことも。ここでは、これら発達障がいについてご紹介しています。
発達障がいのお子さんが不登校になってしまう原因とは?
発達障がいの特性を抱くお子さんは、人間関係や社会性を構築するのが苦手であったり、学校の勉強についていけないなどが原因で孤立したりいじめに合うこともあり、不登校になってしまうケースがあります。
こちらでは、発達障がいの特性別に不登校になってしまう原因と、不登校になった場合に家族や周囲がどのようにサポートすればお子さんが前向きになれるのかなどについて紹介していきます。
発達障がいのお子さんが不登校に
なってしまう原因についてはこちら
発達障がいを抱えるお子さんの高校選びとは
発達障がいを持つお子さんの高校選びは、お子さんの特性に合った高校かどうか・求めているサポートを受けられるか・高校卒業後の進路を考慮したうえで選んでいるかが重要なポイントとなります。
発達障がいの特性は一人ひとり異なるため、お子さんの興味のある分野や配慮・支援が必要な部分を把握したうえで選ぶことが大切です。また、授業の内容や支援体制だけでなく、授業の形式や頻度、卒業に必要な条件を満たせるかどうかもチェックしておきましょう。
こちらでは、発達障がいのお子さんの高校選びで参考にしてほしいポイントと、選べる選択肢について紹介します。
発達障がいをもつ子どもの通信制高校の選び方
周囲の生徒と同じように行動するのが難しい場合、無理して通う事で集団生活に馴染めず、不登校や卒業がむずかしくなってしまうこともあります。障がいの症状は見た目で誰もがわかるものではないので、周囲からの理解がある、特性に合わせた活動ができる環境やサポートを用意してあげる必要があります。
ここでは、発達障がいに悩む方も安心して通える、寄り添ったサポートを提供している通信制高校選びのポイントを紹介しています。
発達障がいがある子どもが高卒資格を目指すには
発達障がいを生徒が通う学校と言えば、特別支援学校(高等部)もしくは高等特別支援学校が知られています。ただ、両校とも卒業して得られるのは大学受験資格のみ。高卒資格ではなく、あくまでも特別支援学校高等部卒業資格となるので、書類上は「中卒」扱いとなります。
発達障がいの生徒が高卒資格を得るには、発達障がいの受け入れ態勢が整っている通信制高校に入学する必要があります。ここでは、発達障害でも難なく高卒資格が取得できる通信制高校についてご紹介しています。
発達障がいを抱えるお子さんの高校卒業後の進路とは?
近年は発達障がいを抱えながら大学・短大に通学する学生も増えています。高校卒業後、進学する場合は「卒業まで学習を維持できるか」「興味のある内容が学べるか」「通学に際し支援を受けられるか」などを考慮することが大切です。
また、就職・進学だけでなく、就職に向けた支援を受けることも選択肢に入れておきましょう。こちらでは、発達障がいを抱えたお子さんの高校卒業後の選択肢について紹介します。
発達障がいを抱えるお子さんの高校卒業後の進路についてはこちら
高校では発達障がいに対してどのような配慮を受けられる?
2016年に「障害者差別解消法」が施行されました。この法律は、障がいによる差別をなくすために学校や企業、行政に対して障がいの特性を持つ方に対して可能な限り「合理的配慮」を行うよう求めています。つまり、高校においても座席の配慮や静かな環境の提供、避難や相談できる場所の確保、課題の進め方など生徒の特性に応じた配慮を受けられるように教育現場が変わりつつあるのです。こちらでは発達障がいを抱える生徒に対する合理的配慮についてまとめています。
高校では発達障がいに対して
どのような配慮を受けられる?はこちら
知的障がいとは?発達障がいとの違い
知的障がいは「精神遅滞・精神発達遅滞」とも呼ばれて、知的機能が同世代の水準を下回り、社会生活の適応や日常生活が困難な状態のことを指します。
生まれながらにして脳機能の障がいが原因とされる“発達障がい”に対し、知的障害は先天的な要因だけでなく後天的なことが要因で起こるケースがあります。また、知的障がいと発達障がいは別の特性である一方で、両方の特性を持つ人も存在します。
こちらでは、知的障がいの特性や分類、発達障がいとの違いについて詳しく紹介していきます。
知的障がい・境界知能を持つお子さんの高校選び
知的障がいの特性を抱えているお子さんの高校進学は、特別支援学校高等部が適切だと言われています。しかし軽度の知的障がいであったり、境界知能(グレーゾーン)領域と診断されているお子さんであれば、通信制高校も視野に入れることも可能です。
こちらでは、主に軽度知的障がいと境界知能のお子さんの高校進学の選択肢や特別支援学校の特徴、お子さんの特性に合う高校選びのポイントなどについて詳しく紹介します。ぜひ参考にしてください。
知的障がいのあるお子さんの進路とは?
特別支援学校高等部や通信高校などを卒業した知的障がい者の進路は、進学よりも就職を目指す方向を選択する方が圧倒的に多いのが現状です。その場合、卒業後すぐに就職するケースもあれば、福祉事業所へ通所して就労に必要な知識やスキルを身に付けてから職に就くケースなどさまざまな方法があります。こちらでは、知的障がいのあるお子さんの進路先として主な方向と、利用する可能性が高い就労支援施設の概要を紹介しています。
知的障がいのお子さんに対する合理的配慮とは?
2016年4月に障害者差別解消法が施行されたことで、障がいのある方に対して合理的配慮の提供が義務化されました。これは障がいを抱えるか否かに関係なく全ての人が平等であることを基本とし、人権と基本的な自由を当たり前に行使できるように配慮するものです。
教育現場においては、知的障がいを抱えるお子さんに対してわかりやすくゆっくりとした言葉かけをしたり、理解しやすいような教材(フラッシュカードや絵カード、数え棒など)を使う、伝えたことを確認するため聞き直す、などの配慮例があります。
知的障がいがある場合でも一人暮らしは可能?
知的障がいを抱える方の多くは、家族やグループホームの施設で暮らしていますが、中には「自立をしたい」という希望を持つ方や、やむを得ない事情で一人暮らしをしなくてはならない方もいることでしょう。
障がいを持つ方の一人暮らしは健常者に比べて課題が多いため、これから一人暮らしをしようとする方は障がい者福祉支援の窓口に相談して適切な支援を受けることをおすすめします。こちらでは、一人暮らしをする上での注意点や福祉支援制度についてまとめています。
知的障がいのお子さんへの接し方とは?
知的障がいの特性を持つお子さんは、個人差はあるものの、ある程度共通した困りごとを抱えています。例えば、言語や数字などの理解が年相応よりも遅れているため、興味のないことには集中できなかったり、誰かと社会的関係を築くことが苦手であったり、記憶することを苦手としているため、効率良く行動できないなどです。周囲の方は、こういった特性を理解したうえで、適切に接すれば、知的障がいのお子さんともコミュニケーションをとることができます。
境界知能とは?知的障がいとの違いや困りごと
境界知能とは、平均的な知能指数(IQ)と知的障がいと診断される知能指数との狭間領域のことを呼びます。ただし境界知能やグレーゾーンという言い方は、医学的な診断名ではなくてあくまでも“通称”です。日常生活は大きな支障なく送れるために、周囲からは境界知能である認識をしてもらえず一人で悩みを抱える方も多くいます。
こちらでは、そんな境界知能の特徴や知的障がいとの異なる点、境界知能を抱えることによる困りごとなどを紹介していきます。
発達障がいのあるお子さんが自立するために
発達障がいのあるお子さんが将来自立して生活できるようになるためには、早い段階からの準備と、家庭や学校、支援機関による継続的なサポートが大切です。こちらではお子さんの自立に向けた支援の考え方や、家庭・学校・地域の支援機関でできるサポートについて紹介しています。
軽度知的障がい・発達障がいの
お子さんでも
通いやすい
「興学社高等学院」の魅力とは
軽度・中低度知的障がいやグレーゾーンの
お子さまも安心の学び場

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/)
大切なお子さんが軽度・中低度知的障がいや発達障がい、グレーゾーンであるとして診断を受けていると、今後の将来についてどうしても不安になってしまうでしょう。
しかし興学社高等学院では、障がいがない生徒に接するのと同様に、一人ひとりに共感して寄り添いながら、得意なことを好きなように学ぶことができる環境が整っています。
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)で、社会生活や人間関係に適応する力を養う
- 子どもの特性を知るWISC-IV検査を実施し、一人ひとりの“得意”を伸ばす
- 高校卒業資格取得率98.9%※、単位取得へのフォローが手厚い
※参照元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/characteristics)令和2年度時点の実績
感覚を活かす実践型の授業で、自信を育てる

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
興学社高等学院のリベラルアーツ科では、視覚や聴覚などの「五感」を活かした体験型の授業が中心です。たとえば職業体験や実習を通じて、実際に体を動かしながら学ぶことで、机上の勉強が苦手なお子さんも「できた!」という達成感を得やすくなっています。
また、感覚の特性に配慮したカリキュラムや、行動の背景を理解して支援する「応用行動分析」の考え方も取り入れ、一人ひとりに合った学び方ができます。「わかる」「できる」を積み重ねることで、お子さんの自信と将来への希望が育ちます。
保護者・在校生の声

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
▼ 保護者の声 ▼
- 入学時は教室にも入れず、友達も作れずなかなか学校に行くことが出来なかった息子ですが先生方は子供に寄りそい、声をかけとても親身にやって下さいました。おそらくそれぞれのお子さんに合わせた指導をされていると思います。
- うちの息子はコミュニケーション能力が低く、高校生活を送れるか心配でしたがだんだんと先生方にも慣れ、本人のペースではありますがなんとか続けられました。先生方には特には厳しく、時には優しく、寄りそって下さり息子本人も親も興学社に来てよかったと感謝しておりま す。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/parents)
▼ 生徒の声 ▼
- 私は中学校の時、いつもクラスで静かで誰とも話せませんでした。そんな時、興学社高等学院のことを知り入学してみると、先輩や先生方はとても優しく接してくださり、困ったことがあってもすぐに相談にのってくれるため、とても嬉しかったです。(後略)
- 最初は何も分からなくて、毎日、不安だらけでした。勉強も苦手で、友だち作りも苦手で…でも興学社高等学院の先生は、そんな苦手だらけの私にいつも優しく接してくれました。そして、少しずつ自分に自信が持てるようになりました。これからは、お母さんを助けていきたいです。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/student)
▼ 千葉県の新松戸校はコチラ ▼
▼ 埼玉県の新越谷校はコチラ ▼
▼ 興学社高等学院のサポート内容や授業風景・口コミをもっと見るならコチラ ▼
- 発達障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいのお子さんが不登校になってしまう原因とは?
- 境界知能とは?知的障がいとの違いや困りごと
- 知的障がいがあっても自立した一人暮らしは可能?
- 知的障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいの種類
- 発達障がいを抱えるお子さんの高校選びとは
- 発達障がいをもつ子どもの通信制高校の選び方
- 発達障がいがある子どもが高卒資格を目指すには
- 発達障がいを抱えるお子さんの高校卒業後の進路とは?

興学社高等学院に通う生徒とその保護者、先生からそれぞれの口コミ評判を集めました。 実際に学校に関わっている人達だからからこそ出てくる生の声を、ぜひチェックしてみてください。