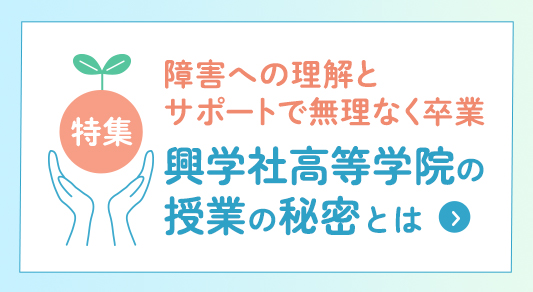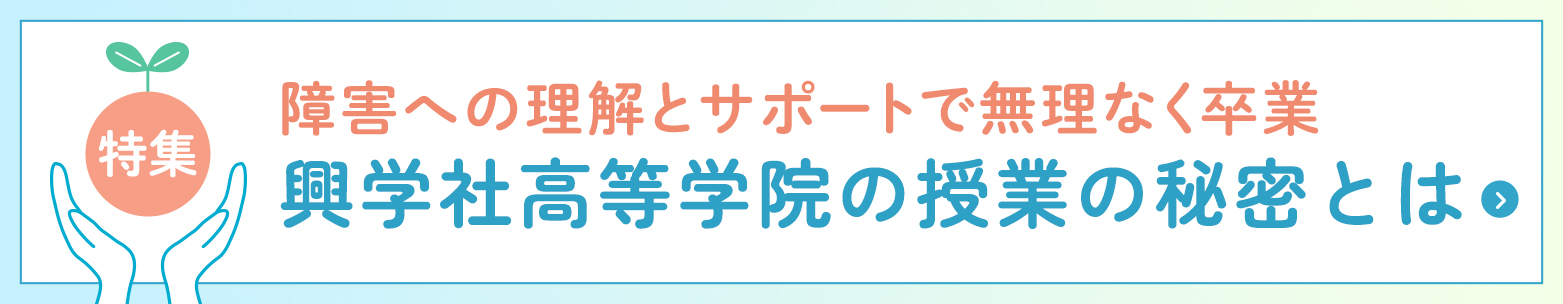知的障がいのお子さんへの接し方とは?
個人差はありますが、知的障がいを抱えるお子さんには、共通してみられる困りごとがあります。保護者の方や周りの方は、そういった障がいの特性を配慮したうえで接したり、伝えていくことが大事です。ここでは、知的障がいのお子さんへの接し方について紹介していきます。
知的障がいのお子さんが躓きやすいポイント
集中力・注意力を持続させるのが難しい
知的障がいの特性を持つ方の中には、発達障がいの特性であるADHD(注意欠如多動症)を併存している方もいます。今行っている作業や人の話に集中できなかったり、短時間しか持続できない、思いついた別の行動をしてしまうなどです。また知的障がいの方は記憶や認知するのが苦手な方が多いため、長時間授業に注意を向けるのが難しいという理由も挙げられます。
抽象的な物事への理解が追いつきにくい
知的障がいの特性を抱える方は、「自分の身の回りにある具体的な物を基本にして外界を認識する」傾向があります。そのため、目の前にないものを頭で描いたり、“時間”や“数”という概念を理解したり、経験したことのないことを想像するのが難しいと言われています。
例えば「あと少しで終わります」と伝えても、“あと少し”という曖昧な表現がどの程度の時間であるのか理解できないお子さんがいるのです。
コミュニケーションにおける困難
知的障がいの特性には会話や言葉の遅れがあったり、言語そのものの概念が難しくて、相手の言っている言葉を理解するのが困難な場合があります。このような理由があるため、知的障がいの特性を持つお子さんは、人とコミュニケーションをとることが難しいケースが多く、自分の気持ちを上手く伝えることができないと、相手を叩くなどの行為をしてしまうお子さんもいます。
知的障がいを持つお子さんへの接し方
絵や図を使って具体的に伝える
知的障がいの特性を抱えるお子さんは、目に見えない概念や抽象的なことを、経験したことのないことを理解するのが苦手なケースが多いため、実物や絵、写真などを活用した視覚的な情報とともに具体的に伝えたり、一緒に行動して実体験を繰り返すと理解しやすくなります。
また、手順をなかなか覚えられないときは、イラストや写真などと一緒に行う順番を記した絵カードを使うのもおすすめです。
曖昧な表現を使わない
知的障がいを抱えるお子さんの中には、曖昧な表現を理解するのが苦手なことが多いです。
例えば「あと少しで授業が終わる」という表現も、一般的な感覚であれば時計を確認したり、授業開始から過ごした体感からあと5分位で終了かな、と理解できますが、知的障がいのお子さんにとっては、「少し」が5分なのか30分なのか感覚がつかめません。
「きちんと片づけて」という表現も、“きちんと”とは、何をどのように片づけていいのかわからないから行動に移せないこともあります。知的障がいを抱えるお子さんに接する時は、「あと3分で授業が終わる」や「洋服はタンスに仕舞って、本は本棚に戻して」など具体的に話しかけるようにしましょう。
一つずつ説明する
一度にいくつもの指示をすると知的障がいのお子さんは混乱したり、2つ目以降の指示を忘れてしまったりすることがあります。「一時一事の原則」をできるだけ守り、1度目の指示が終わったことを確認してから次の指示を伝えるようにしましょう。
例えば「黒板の文字をノートに書き写して10回繰り返す練習して」という場合は、「黒板の文字をノートに書き写す」と「その文字を10回練習する」を別々に指示すると理解してもらいやすくなります。
褒めるときははっきりと
お子さんに成功体験を味わってもらうことも大切です。特に思春期のお子さんは、他の人ができることが自分にできないと劣等感を持つお子さんもいるでしょう。できないこと、苦手なことばかりに目を向けて自信を失くしてしまわないように、できたこと、正しいことをした時には、お子さんに伝わるようにはっきりと褒めてあげましょう。
お子さんの得意なことや夢中になれる環境を用意して「できた!」という実感につながるようにしても良いでしょう。
軽度知的障がい・発達障がいの
お子さんでも
通いやすい
「興学社高等学院」の魅力とは
軽度・中低度知的障がいやグレーゾーンの
お子さまも安心の学び場

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/)
大切なお子さんが軽度・中低度知的障がいや発達障がい、グレーゾーンであるとして診断を受けていると、今後の将来についてどうしても不安になってしまうでしょう。
しかし興学社高等学院では、障がいがない生徒に接するのと同様に、一人ひとりに共感して寄り添いながら、得意なことを好きなように学ぶことができる環境が整っています。
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)で、社会生活や人間関係に適応する力を養う
- 子どもの特性を知るWISC-IV検査を実施し、一人ひとりの“得意”を伸ばす
- 高校卒業資格取得率98.9%※、単位取得へのフォローが手厚い
※参照元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/characteristics)令和2年度時点の実績
感覚を活かす実践型の授業で、自信を育てる

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
興学社高等学院のリベラルアーツ科では、視覚や聴覚などの「五感」を活かした体験型の授業が中心です。たとえば職業体験や実習を通じて、実際に体を動かしながら学ぶことで、机上の勉強が苦手なお子さんも「できた!」という達成感を得やすくなっています。
また、感覚の特性に配慮したカリキュラムや、行動の背景を理解して支援する「応用行動分析」の考え方も取り入れ、一人ひとりに合った学び方ができます。「わかる」「できる」を積み重ねることで、お子さんの自信と将来への希望が育ちます。
保護者・在校生の声

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
▼ 保護者の声 ▼
- 入学時は教室にも入れず、友達も作れずなかなか学校に行くことが出来なかった息子ですが先生方は子供に寄りそい、声をかけとても親身にやって下さいました。おそらくそれぞれのお子さんに合わせた指導をされていると思います。
- うちの息子はコミュニケーション能力が低く、高校生活を送れるか心配でしたがだんだんと先生方にも慣れ、本人のペースではありますがなんとか続けられました。先生方には特には厳しく、時には優しく、寄りそって下さり息子本人も親も興学社に来てよかったと感謝しておりま す。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/parents)
▼ 生徒の声 ▼
- 私は中学校の時、いつもクラスで静かで誰とも話せませんでした。そんな時、興学社高等学院のことを知り入学してみると、先輩や先生方はとても優しく接してくださり、困ったことがあってもすぐに相談にのってくれるため、とても嬉しかったです。(後略)
- 最初は何も分からなくて、毎日、不安だらけでした。勉強も苦手で、友だち作りも苦手で…でも興学社高等学院の先生は、そんな苦手だらけの私にいつも優しく接してくれました。そして、少しずつ自分に自信が持てるようになりました。これからは、お母さんを助けていきたいです。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/student)
▼ 千葉県の新松戸校はコチラ ▼
▼ 埼玉県の新越谷校はコチラ ▼
▼ 興学社高等学院のサポート内容や授業風景・口コミをもっと見るならコチラ ▼
- 発達障がいのあるお子さんが自立するために
- 発達障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいのお子さんが不登校になってしまう原因とは?
- 境界知能とは?知的障がいとの違いや困りごと
- 知的障がいがあっても自立した一人暮らしは可能?
- 発達障がいの種類
- 発達障がいを抱えるお子さんの高校選びとは
- 発達障がいをもつ子どもの通信制高校の選び方
- 発達障がいがある子どもが高卒資格を目指すには
- 発達障がいを抱えるお子さんの高校卒業後の進路とは?

興学社高等学院に通う生徒とその保護者、先生からそれぞれの口コミ評判を集めました。 実際に学校に関わっている人達だからからこそ出てくる生の声を、ぜひチェックしてみてください。