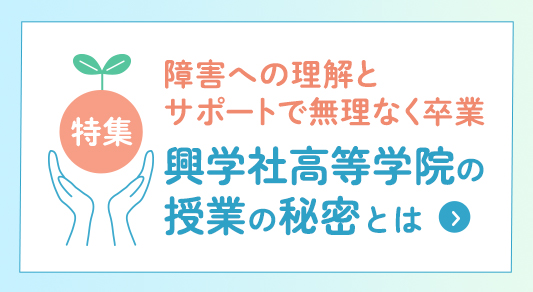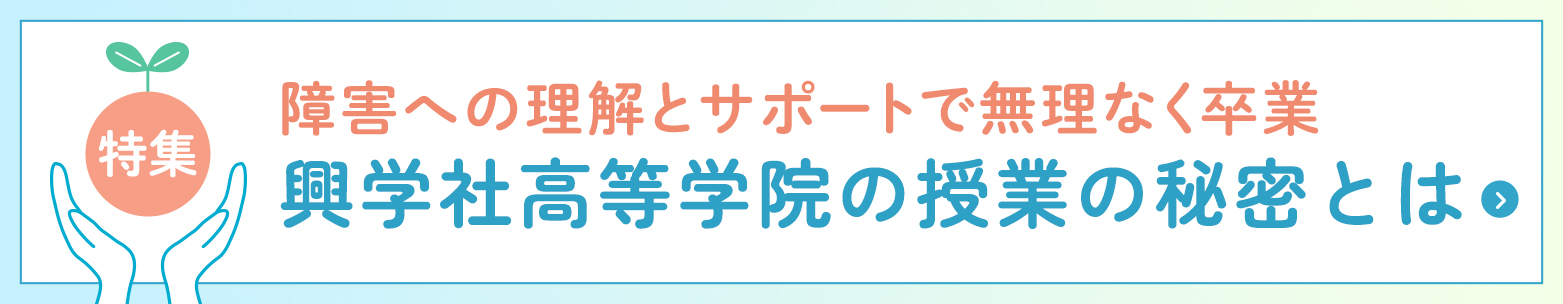発達障がいを抱えるお子さんの高校選びとは
発達障がいを抱えるお子さんの高校進学について、「どんな高校へ行けるのか」「どのように学校選びをすればよいのか」など不安や疑問を抱いている保護者の方は多いかと思います。
もちろん、たとえ発達障がいという特性を持っているお子さんであっても、入試の得点や内申点が合格基準を満たしていれば全ての学校に通うことができます。しかし、入学後にお子さんが安心して通える学校を選ぶには、それぞれの学校の方針や学べる内容、通学頻度を確認したうえで選ぶ必要があるでしょう。特に発達障がいの特性によっては、授業の形式や雰囲気などが高校選びにおいて重要なポイントになります。
こちらでは、お子さんが “通いやすい” と感じられる学校選びのために知っておきたい基礎知識と、選ぶうえでのポイントを紹介します。
通える高校の選択肢は?
まずは、日本国内において高校卒業の資格が取れる高等学校の種類と概要を簡単に紹介していきます。
高校の種類
全日制高校
全日制高校とは、月曜から金曜日の昼間(7~8時間)に授業時間を設けている高等学校を指し、全高校生の約9割強がこのスタイルの高校に通学しています。中学卒業後にそのまま全日制高校へ進むケースが多く、3年間の学年制がほとんど。成績や出席数などが満たなければ進学できないケースもあります。
定時制高校
定時制高校は、全日制高校と同様に平日に通学して学ぶスタイルですが、夜間や日中の短時間(3~4時間)授業を行っている高校のことです。「働きながら」や「不登校経験があり進学が出遅れてしまった」「経済的理由」などの事情を抱えるケースが多いようです。そのため通学する生徒の年齢層は広いのが特徴です。
通信制高校
通信制高校は、全日制や定時制のように毎日登校する必要がなく、通信教材やオンラインなどで学習を進めます。課題に対するレポートの提出と年間決められたスクーリング(登校)、単位取得のための試験をこなして決められた単位を取得して高校卒業を目指します。
特別支援学校
特別支援学校は、障がいを持つお子さんの自立や社会参加に向けて、生活・学習で困る場面を解決できるよう指導・支援することを目的とした学校です。基本的に視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい・肢体不自由・身体虚弱などの生徒を対象にしており、教育委員会へ就学希望を申し込む必要があります。
都道府県ごとに設置している特別な学校
都道府県によっては不登校の生徒や発達障がいの生徒に向けて、一人ひとりに柔軟に対応できるような高校を設置しています。これらの高校は、多様なニーズに応えるべく従来の学校システムにない独自の環境を提供しており、通学する時間や学べるカリキュラムなども選択できるよう配慮されているのが特徴です。
これから紹介するスクールは、既に実施されている教育システムの一例です。各自治体ごとに名称・実施時期が異なるため、お子さんの校区や住んでいる都道府県で調べてみることをお勧めします。
チャレンジスクール(東京都)
不登校の経験のある生徒や、長期欠席などの理由で高校中退した生徒などを受け入れる定時制・単位制の東京都立高校のこと。午前部・午後部・夜間部から選べ、基本的には4年間で卒業するペースで平日に通学して学習する。
エンカレッジスクール(東京都)
「エンカレッジ:encourage」は、励ますや力づけるという意味。不登校などで小・中学校では十分な能力を発揮できなかった生徒に寄り添い、再び学習への意欲を取り戻すことを目的にした全日制のスクール。
トライネットスクール(東京都)
インターネットを活用して大学進学や資格取得など、生徒のニーズに応じたカリキュラムを設けて高校卒業を目指すスタイル。「学校に通えない生徒のセーフティ“ネット”」「インター“ネット”を取り入れた教育」「都立高校の“ネット”ワークを活かした幅広い科目」という3本のモットーが基本になっている。
パレットスクール(埼玉県)
不登校経験者や高校中退、働きながら学習したいという生徒のために設けた多部制の定時制高校。地域バランスと交通の利便性を考慮して設置されている。午前部、昼間部の2部制定時制高校と、夜間部もある3部制定時制高校がある。
クリエイティブスクール(神奈川県・大阪府)
小・中学校時代に実力を発揮できなかった生徒に対し、芸術や音楽、デザインなどの領域に重点をおいてクリエイティブな表現やアーティスティックな学びの場を提供するスクール。生徒の個性を尊重して自己表現の場を設けている。
フレキシブルスクール(神奈川県)
神奈川県川崎市や厚木市など実施しているスクールで、生徒のライフスタイルや学習ニーズ、ペースに合わせ、多様な学びの方法を取り入れながら昼夜間の幅広い授業時間帯に柔軟に学べる単位制高校のこと。
フロンティアスクール(神奈川県)
午前部、あるいは午後部に分けて、1日約4時間の授業内容をひとり一人のペースに合わせてゆっくりじっくり学ぶスタイル多部制定時制高校のこと。基本的に4年間で卒業を目指す。
公立か私立か
公立高校と私立高校のどちらを選ぶべきかは、「どれぐらいの支援が必要か」「求めるサポートはどの程度か」に大きく依存します。公立高校の場合、学費を抑えられるというメリットがあるものの、学習面・メンタル面におけるサポート体制には限界がある場合があります。それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで選ぶことが大切です。
公立高校への進学
学力試験の点数や内申点に問題がなければ、公立の全日制高校に通うことも可能です。しかし、発達障がいに応じたサポートが期待できるか、という点においては公立高校では難しいと言わざるを得ません。
高校では中学時代よりも自発的な活動が多くなるため、対人関係やコミュニケーションに問題を感じているお子さんの場合、どうしても躓いてしまう傾向にあります。またある程度の成績や出席率を保つ必要があるため、学力水準やカリキュラムに問題なくついてけるかどうか、気を配る必要があります。
生徒数が多く、メンタル面・学習面におけるケアが薄い公立高校では、不安障がいといった二次障がいを引き起こす可能性も考えられるでしょう。
もちろん、これらのデメリットが発達障がいの特性を持つ全ての生徒に当てはまるわけではありません。気の合う友達や相談できる教師を見つけて、楽しいスクールライフを送る生徒もいます。公立の全日制高校へ通学したいと本人が強く望んでいるのであれば、校風や学校の受け入れ態勢などを確認したうえで選ぶと良いでしょう。
私立高校への進学
公立高校に比べると、私立高校の方が発達障がいを抱える生徒の受け入れ体制が整っているケースが多いと言えるでしょう。運営方針や教員教育の決定権が学校法人側にあるため、指導方針や教育内容が一貫していることが一因として挙げられます。
心理士やスクールカウンセラーが常駐している高校も多く、教師の移動も少ないため発達障がいを理解してくれるような先生に巡り合えれば、恵まれた環境でスクールライフを送れる可能性が高いでしょう。
ただし、全ての私立高校がそうであるとは限らないため、事前にリサーチすることが大切です。
発達障がいを持つ子どもの高校選びなら
通信制高校がおすすめ
受験ハードルが低く
入学しやすい
通信制高校への入学では年齢制限がなく、学力試験を実施しないところがほとんどです。実施していたとしてもごく簡単な筆記試験のみで、公立の通信制高校に多く見られます。
そのテストも現在の学力を見る事を目的にしており、合否はテストの点数ではなく作文と面接で判断されています。生活態度や試験態度に問題がない限り、不合格になることは殆どありません。受験を申し込み、当日に欠席することなく受けられた方は、基本的に合格できます。
発達障がいがある子どもへの
サポートが手厚い
少人数制で目が行き届く体制や個別指導対応など、生徒一人ひとりの特性に寄り添ったサポート体制が整っている学校であれば、集団が苦手な子どもでも安心して通うことができます。クラスを固定しない自由なスケジュール調整が可能な環境は、人間関係のストレスを軽減し、落ち着いて学習に取り組めるのも大きな利点です。特に発達障がいのある子どもにとっては、自分のペースで学べる通信制高校は、感覚過敏や集中力の波といった特性にも柔軟に対応できるため、無理なく学びを継続できます。
技能連携校という選択肢も
技能連携校とは、「技能連携制度」を利用して、専門的な学びと通信制高校での普通科目の学習を両立できる学校のことです。
具体的には、商業・工業・情報・福祉などの実務的な分野を学べる高等専修学校に入学すると同時に、通信制高校にも在籍し、3年間で2つの学校を卒業できる仕組みになっています。
技能連携校では「職業や生活に役立つ専門スキルを身につけること」を目的としており、専門学校や有名企業、学習塾や全日制高校を運営している法人などが設置しています。ただし、英語・数学・国語といった普通科目は設けられていないため、通信制高校と連携して学ぶ形になります。
「2つの学校に通うなんて大変そう…」と思う方もいるかもしれませんが、技能連携校で学ぶ専門科目の一部は通信制高校の単位として認められます。そのため、効率的に専門分野を学びながら高卒資格の取得を目指せるのが大きな特徴です。
技能連携校のメリット
技能連携校では、通信制高校の卒業に必要な単位を得られると同時に、社会に出てから役立つ専門スキルを身につけることができます。専門分野の教育に必要な設備やカリキュラムが整っているため、卒業後すぐに仕事に活かせる知識や技術を身につけられるのは大きな魅力です。
つまり、技能連携校に通うことで「高卒資格」と「専門的なスキル」の両方を得られる点は、通信制高校単体では得られないメリットといえるでしょう。
技能連携校とサポート校の違い
技能連携校とサポート校の大きな違いは「単位の扱い」にあります。
技能連携校での授業は「技能連携制度」に基づき通信制高校の単位として認められますが、サポート校での授業は単位にはならず、あくまで学習面での補助を行うことを目的としています。
また、技能連携校の場合は、通信制高校のスクーリングを提携している専修学校で受けられるのも特徴です。サポート校との違いを知ることで、お子さんに合った進路をより具体的に考えやすくなるでしょう。
発達障がいの
お子さんでも通いやすい
技能連携校「興学社高等学院」の魅力とは

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/)
発達障がいの
お子さまも安心の学び場
大切なお子さんが発達障がいであるとして診断を受けていると、今後の将来についてどうしても不安になってしまうでしょう。
しかし興学社高等学院では、障がいがない生徒に接するのと同様に、一人ひとりに共感して寄り添いながら、得意なことを好きなように学ぶことができる環境が整っています。
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)で、社会生活や人間関係に適応する力を養う
- 子どもの特性を知るWISC-IV検査を実施し、一人ひとりの“得意”を伸ばす
- 高校卒業資格取得率98.9%※、単位取得へのフォローが手厚い
※参照元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/characteristics)令和2年度時点の実績
感覚を活かす実践型の授業で、自信を育てる

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
興学社高等学院のリベラルアーツ科では、視覚や聴覚などの「五感」を活かした体験型の授業が中心です。たとえば職業体験や実習を通じて、実際に体を動かしながら学ぶことで、机上の勉強が苦手なお子さんも「できた!」という達成感を得やすくなっています。
また、感覚の特性に配慮したカリキュラムや、行動の背景を理解して支援する「応用行動分析」の考え方も取り入れ、一人ひとりに合った学び方ができます。「わかる」「できる」を積み重ねることで、お子さんの自信と将来への希望が育ちます。
保護者・在校生の声

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
▼ 保護者の声 ▼
- 入学時は教室にも入れず、友達も作れずなかなか学校に行くことが出来なかった息子ですが先生方は子供に寄りそい、声をかけとても親身にやって下さいました。おそらくそれぞれのお子さんに合わせた指導をされていると思います。
- うちの息子はコミュニケーション能力が低く、高校生活を送れるか心配でしたがだんだんと先生方にも慣れ、本人のペースではありますがなんとか続けられました。先生方には特には厳しく、時には優しく、寄りそって下さり息子本人も親も興学社に来てよかったと感謝しておりま す。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/parents)
▼ 生徒の声 ▼
- 私は中学校の時、いつもクラスで静かで誰とも話せませんでした。そんな時、興学社高等学院のことを知り入学してみると、先輩や先生方はとても優しく接してくださり、困ったことがあってもすぐに相談にのってくれるため、とても嬉しかったです。(後略)
- 最初は何も分からなくて、毎日、不安だらけでした。勉強も苦手で、友だち作りも苦手で…でも興学社高等学院の先生は、そんな苦手だらけの私にいつも優しく接してくれました。そして、少しずつ自分に自信が持てるようになりました。これからは、お母さんを助けていきたいです。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/student)
▼ 千葉県の新松戸校はコチラ ▼
▼ 埼玉県の新越谷校はコチラ ▼
高校進学における主なハードル
学習面での困難
発達障害をもつ子どもは、集中力の持続や情報の処理が難しい場合があります。授業のスピードについていけなかったり、課題提出の管理が負担になることも少なくありません。そのため、学習面でのつまずきが高校生活全体に影響を与えるケースがあります。
対人関係の難しさ
友人関係の構築や集団でのコミュニケーションも大きな課題です。言葉のニュアンスを読み取りにくかったり、会話のテンポが合わずに誤解を招くことがあります。孤立感を抱くことで、不登校につながるケースもあるため、周囲の理解や支援が欠かせません。
環境変化への対応
中学校から高校へ進学すると、通学環境や生活リズムが大きく変わります。教科ごとに先生が変わることや、クラス編成のがストレスとなることもあります。新しい環境に適応するには時間がかかるため、段階的に慣れていける工夫が必要です。
発達障がいを持つ子どもの高校選びで確認すべき4つのポイント
お子さんにとって最適な学習環境を選ぶためには、「どんな支援を求めているのか」「何を目指しているのか」「何を学びたいのか」を保護者とお子さんで改めて確認することが重要です。こちらでは、高校選びの前に押さえておくべき点を4つに整理して紹介します。
子どもの特性を把握する
発達障がいには広汎性発達障がいや学習障がい(LD)、注意欠如・多動性障がい(ADHD)などの他に、発達障がいの傾向が見られるグレーゾーンのお子さんもいます。
それぞれによって悩み事や特性には傾向があるものの、「どの特性が強いのか」や「体調・状況など条件によって違う」などについては一人ひとり異なるため、お子さんが「どの条件で、どの程度サポートしてほしいのか」を明確にする必要があるでしょう。
特にグレーゾーンのお子さんの場合、それぞれの障がいの特性を複数抱えているケースがあります。どういうタイプであるかを正確に把握することで、学校側に求める支援や受けられるアプローチの質が変わるため、学校を選ぶ前に改めて把握する事が大切です。
進学後のサポート内容・支援体制を確認する
学校の支援体制や方針は、各校によって異なります。せっかく入試に合格して進学しても、学校側の発達障がいを抱える生徒のサポートが未熟であったり、支援環境が整っていなければ、うまく通えなくなるケースも考えられます。学校のサポート内容や特徴がお子さんに合っているかどうか、事前に確認することが重要です。
「支援はあるけど、求めている内容ではない」というケースもあります。特に全日制高校の場合、発達障がいの受け入れ体制については公表していないケースがほとんど。カウンセラーの在籍有無や、発達障がいの子どもに対する個別カリキュラムの用意はあるのかなど、直接問い合わせることも検討しましょう。
高校卒業後の進路をすり合わせる
高校を選ぶ際には「高校卒業後の進路」も考慮に入れましょう。近年では、普通科に加えてIT分野・アニメ・漫画・芸能・美容・デザインなど、さまざまなジャンルを学べるスクールも増えています。また、将来的な社会生活を見据えて、コミュニケーションや対人関係、生活の基礎知識に関する指導を行っている学校もあります。
高校卒業資格を取得するだけでなく、「進学・就職どちらに向けたサポートを受けるべきか」を決めるために、まずはお子さんの進路を考えてみることも大切です。
子どもの意思を確認する
高校選びを保護者優先で決めるのは危険と言えます。発達障がいのお子さんは強いこだわりを持っていることも少なくないため、意にそぐわない決定をしてしまうと通学のモチベーションが下がり、不登校や退学に繋がる可能性があるでしょう。
保護者の冷静な意見ももちろん重要ですが、大切なのは、お子さんにいろいろな選択肢があることを教えてあげること。情報を与えることで選択肢が広がり、お子さんの視野も広がります。そのうえで、どのような通学スタイルがよいのか、学びたい分野や将来の希望などの意思を確認し、必要ならば専門家と一緒に意見をすり合わせて学校選びを進めましょう。
発達障がいの子どもの進学先で留意すべき点
発達障がいがあることを伝える
「発達障がいを抱えていると知られたら、それを理由に合格できないかもしれない」と心配される保護者もいるかもしれませんが、高校に入学する前に、あるいは学校を決める前にお子さんの特性を包み隠さず学校側に相談するようにしましょう。
お子さんの特性を伝えず入学した場合、学業やスクールライフで困難な状態になったとしても学校側は何も知らずに接するため、結果的に苦労したり悩んでしまったりする可能性があります。そういった状況に陥らないために、入学前に高校側と情報を共有して、協力体制を築くようにしましょう。
学校見学・オープンキャンパスに参加する
学校見学やオープンキャンパスなどに積極的に参加して、実際の学校の雰囲気を掴んでおきましょう。実際に教師や生徒と接することで、お子さんに合う環境であるのかを肌で感じられます。また、校舎のアクセス環境が通学するのに現実的な距離・状態かどうかは、高校の公式サイトや資料だけの情報では不十分なケースも。不明点などは教師に直接質問することもできるので、参加してもほとんど損はないでしょう。
学校の支援体制や個別支援の特徴を確認する
発達障がいを抱える生徒に対する支援体制は、各学校によって大きく異なります。常勤のスクールカウンセラーやソーシャルワーカーがいる・個別の特別カリキュラムがあるなどの支援体制が手厚い学校もあれば、そういったサポート体制が全くない高校もあります。
支援体制の確認ポイントは下記の通りです。
- スクールカウンセラーやサポート人員が常時在籍しているかどうか
- 個別のカリキュラムや支援があるかどうか
- 通級指導があるかどうか
- 入試時に特別な試験優遇措置があるかどうか
こういったサポート体制を設置している高校であれば、お子さん本人も安心して通学できるでしょう。
軽度知的障がい・発達障がいの
お子さんでも
通いやすい
「興学社高等学院」の魅力とは
軽度・中低度知的障がいやグレーゾーンの
お子さまも安心の学び場

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/)
大切なお子さんが軽度・中低度知的障がいや発達障がい、グレーゾーンであるとして診断を受けていると、今後の将来についてどうしても不安になってしまうでしょう。
しかし興学社高等学院では、障がいがない生徒に接するのと同様に、一人ひとりに共感して寄り添いながら、得意なことを好きなように学ぶことができる環境が整っています。
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)で、社会生活や人間関係に適応する力を養う
- 子どもの特性を知るWISC-IV検査を実施し、一人ひとりの“得意”を伸ばす
- 高校卒業資格取得率98.9%※、単位取得へのフォローが手厚い
※参照元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/characteristics)令和2年度時点の実績
感覚を活かす実践型の授業で、自信を育てる

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
興学社高等学院のリベラルアーツ科では、視覚や聴覚などの「五感」を活かした体験型の授業が中心です。たとえば職業体験や実習を通じて、実際に体を動かしながら学ぶことで、机上の勉強が苦手なお子さんも「できた!」という達成感を得やすくなっています。
また、感覚の特性に配慮したカリキュラムや、行動の背景を理解して支援する「応用行動分析」の考え方も取り入れ、一人ひとりに合った学び方ができます。「わかる」「できる」を積み重ねることで、お子さんの自信と将来への希望が育ちます。
保護者・在校生の声

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
▼ 保護者の声 ▼
- 入学時は教室にも入れず、友達も作れずなかなか学校に行くことが出来なかった息子ですが先生方は子供に寄りそい、声をかけとても親身にやって下さいました。おそらくそれぞれのお子さんに合わせた指導をされていると思います。
- うちの息子はコミュニケーション能力が低く、高校生活を送れるか心配でしたがだんだんと先生方にも慣れ、本人のペースではありますがなんとか続けられました。先生方には特には厳しく、時には優しく、寄りそって下さり息子本人も親も興学社に来てよかったと感謝しておりま す。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/parents)
▼ 生徒の声 ▼
- 私は中学校の時、いつもクラスで静かで誰とも話せませんでした。そんな時、興学社高等学院のことを知り入学してみると、先輩や先生方はとても優しく接してくださり、困ったことがあってもすぐに相談にのってくれるため、とても嬉しかったです。(後略)
- 最初は何も分からなくて、毎日、不安だらけでした。勉強も苦手で、友だち作りも苦手で…でも興学社高等学院の先生は、そんな苦手だらけの私にいつも優しく接してくれました。そして、少しずつ自分に自信が持てるようになりました。これからは、お母さんを助けていきたいです。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/student)
▼ 千葉県の新松戸校はコチラ ▼
▼ 埼玉県の新越谷校はコチラ ▼
▼ 興学社高等学院のサポート内容や授業風景・口コミをもっと見るならコチラ ▼
- 発達障がいのあるお子さんが自立するために
- 発達障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいのお子さんが不登校になってしまう原因とは?
- 境界知能とは?知的障がいとの違いや困りごと
- 知的障がいがあっても自立した一人暮らしは可能?
- 知的障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいの種類
- 発達障がいをもつ子どもの通信制高校の選び方
- 発達障がいがある子どもが高卒資格を目指すには
- 発達障がいを抱えるお子さんの高校卒業後の進路とは?

興学社高等学院に通う生徒とその保護者、先生からそれぞれの口コミ評判を集めました。 実際に学校に関わっている人達だからからこそ出てくる生の声を、ぜひチェックしてみてください。