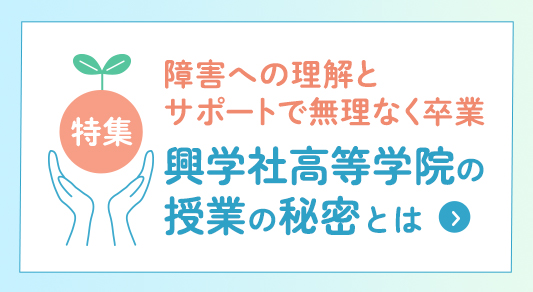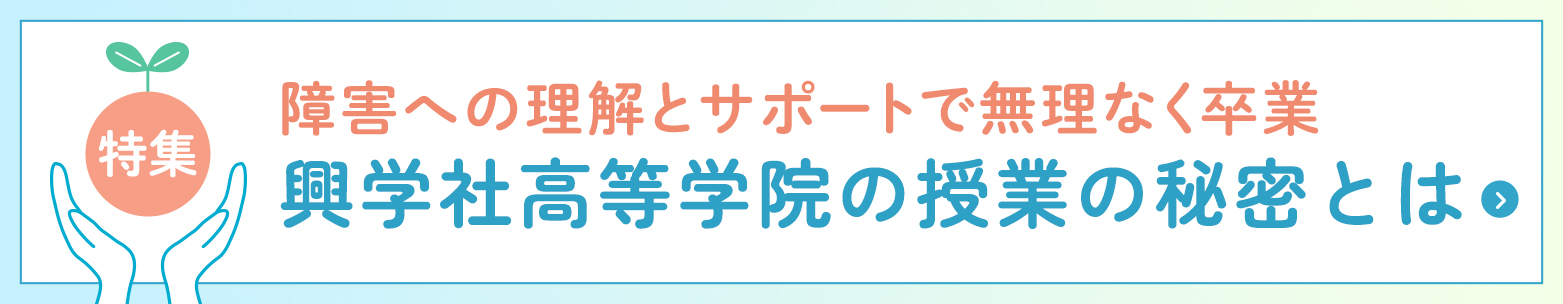知的障がいのお子さんに対する合理的配慮とは?
障がいがあることで学校に登校したり学んだりするのが困難であったり精神的苦痛にならないよう、学校側は生徒に合理的配慮を提供する義務があります。こちらでは合理的配慮の概要や、知的障がいの特性を持つお子さんへの配慮例などを紹介していきます。
そもそも合理的配慮とは
合理的配慮とは、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いを禁止するために2016年4月に施行された「障害者差別解消法」に盛り込まれた障がい者の権利のことです。
「障がいの有無は関係なく全ての人が平等であるということ」を基本な考えとし、障がいや疾患の有無に関わらず同じように社会生活を送れるようにするための環境や設備、支援、サービスを提供する内容となっています。
2024年度から学校法人を含む事業者も義務化へ
2021年に障害者差別解消法が改正されたことでスタートした合理的配慮ですが、これまでは学校などの行政機関が対象でした。しかし2024年4月1日からは民間の事業者に対しても合理的配慮の提供が義務化されるようになりました。
尚、事業者とは次のように定義されています(※)。
- 企業や団体、店舗などの商業施設、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行うものです。
- 個人事業主やボランティア活動のグループも「事業者」に入ります。
もし事業者側が合理的配慮に反する行為を繰り返せば、行政機関から報告を求められたり、指導や勧告を受けることになります。
※参照元:内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」( https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf)
合理的配慮を受けられる対象者は?
合理的配慮を受けられる対象者は、障害者手帳の有無は関係ありません。社会の中において、相当な制限を受けるすべての方が対象となります。もう少し具体的に言うと、身体的であったり知的障がいのある方や精神的な障がいのある方、発達障がいの方、長期にわたり就業生活に制限がある方なども対象になります。
反対に病気やケガなどにより一時的に職業生活に制限を受ける方は対象外です。
実際に学校で実施されている合理的配慮の例
文部科学省では、実際に学校施設においての合理的配慮の指標を項目ごとに示唆しています。こちらでは、各項目の概要と知的障がい者への配慮について文部科学省公式HP「障害種別の学校における合理的配慮の観点(案)」から引用して紹介します。
教育の内容について
教育内容
学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
その障害によって、日常生活や学習場面において様々なつまずきや困難が生じることから、小・中学校等の通常の教育課程による教育にとどまらず、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度、習慣を養うことへの配慮を行う。
- 知的障がいの方への配慮例:
学習や生活に必要で実際的な技術や態度を身に付けられるよう配慮する。(注意深く聞くことや板書などを注視することなど、着替えや持ち物の管理など)
将来の職業生活などに必要な指導を行う。(作業活動、公共機関や交通機関の利用など)
知的障害に伴う認知上の課題(記憶することや文字、形を見分けることが困難など)や身体運動上の課題(ぎこちない動きや微細な作業ができないなど)、情緒の安定に関する課題(興奮しやすい、極端な自信喪失など)に対応した指導を行う。 - 知的障がいの方への配慮例:
年齢を考慮しつつ、生活指導などにおいて、できるだけ実生活につながる技術や態度のための指導目標を設定する。(分担した係仕事をこなす、簡単な調理ができる、小遣い帳を付けることができる、家庭内の仕事ができるなど)
生活指導などにおいて、ルール理解などの実際的な社会性を身に付けていくための指導目標を設定する。(順番を守る、交通ルールを知る、基本的な対人関係のルール、生活に必要な法令を知るなど)
将来の職業生活などに行かせるような指導目標を設定する。(分担した作業に取り組む、責任をもって作業するなど) - 知的障がいの方への配慮例:
教科内容の理解の程度などに応じて、学習内容の焦点化を図り、基礎的で基本的な事項を身に付けられるようにする。
生活上必要な基礎的・基本的な語彙などの意味を確実に理解できるよう配慮する。 - 知的障がいの方への配慮例:
必要に応じて、知的障害に伴う視覚や聴覚などの障害、認知の特性ななどを把握しておく。 - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害の状態に応じて、情報を得られやすくする。(文字の拡大、ルビ付加、話し方の工夫、速さや文の長さの調整、具体的な用語の使用、動作化や視覚化の活用など) - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害に伴う認知や行動の特性、手先の動きの不器用さなどを把握し、教材を工夫する。 - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害の状態に応じて、数量や言語などの理解のための教材などを活用する。(フラッシュカード、文字や数カード、数え棒、パソコンなど) - 知的障がいの方への配慮例:
実際的な生活に役立つ体験ができるようにする。(調理実習、宿泊活動、校外活動など) - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害の状態に応じて、学習の量や学習時間を調整する。(課題数を減らす、時間を延長するなど) - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害に伴う身体全体の運動のぎこちなさや細かな作業の不器用さを補うための工夫をしたり、活動援助の方法やゲームのルールを工夫したりする - 知的障がいの方への配慮例:
学習活動などの予定などを視覚化して分かりやすく表示(図や写真を活用した日課表、活動予定表など)すると共に、予定や準備物を確認できる活動を取り入れる。 - 知的障がいの方への配慮例:
集団の一員として帰属意識がもてるように工夫すると共に、年齢段階を考慮しつつ、徐々に友人関係を築くことが難しくなることに配慮する。 - 知的障がいの方への配慮例:
心理状態や健康状態により、指導内容や方法を柔軟に調整する。
外部からは分かりにくい自尊感情や自己肯定感、ストレスなどの状態を把握する。 - 知的障がいの方への配慮例:
学校生活において、年齢段階を考慮しつつ、知的発達の遅れやそれまでの経験などに応じた役割を分担できるようにする。 - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害のある児童生徒の特徴への対応や提供すべき学習には特別な配慮が必要であることを周囲の児童生徒が理解できるようにする。
知的障害のある児童生徒が不当に自尊感情や自己肯定感が低下することがないように配慮する。 - 知的障がいの方への配慮例:
外部からは分かりにくい知的障害の特性に関する専門性をもつ教員などからの支援を受ける。
外部からは分かりにくい知的障害の特性に関する専門性を含めて、発達段階などをアセスメンする力やそれに基づいた教材などを開発する力をもつ教員を配置する。
必要に応じて、実体験を主とした授業を安全に提供するための適切な人的配置(支援員など)を行う。 - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害のある児童生徒などにとって医療機関とのつながりが重要であることがあることから、必要に応じて、養護教諭を中心に、ニーズに応じて医療機関につなげる窓口を確保する。(てんかん発作など) - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害のある児童生徒が遭遇しやすい「いじめ」予防のための注意を払う。 - 知的障がいの方への配慮例:
外部から分かりにくく、かつ体験が困難な知的障害の特性、及びそれに応じた教育内容などを十分に理解できるように配慮する。 - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害のある児童生徒を専門に教育していて、その積み重ねがある特別支援学校のセンター的機能を活用する。
知的障害に伴う視覚障害などのある児童生徒などに対する適切な指導のために、特別支援学校から支援を受ける。 - 知的障がいの方への配慮例:
療育センターや発達障害者支援センター、その他の福祉関係機関などと連携する。 - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害及びそれに自閉症などを有する児童生徒の緊急時における心理状態を十分に把握しておき、一般の住民と同様には扱えないことに最大限の注意を払う。 - 知的障がいの方への配慮例:
視覚的に動線や目的の場所が理解できるよう配慮を行う。
建物そのものの構造を単純で分かりやすい配置にする。 - 知的障がいの方への配慮例:
衝動的な行動などに対して安全性を確保する。(高所からの落下防止など)
知的障害に伴い免疫機能や体温調節機能が弱い場合があることから、必要に応じて空調などの配慮を行う。
必要に応じて、クールダウンなどのための場所を確保する。
必要に応じて、生活体験を主とした授業を可能にする施設を設ける。 - 知的障がいの方への配慮例:
知的障害及びそれに自閉症などを有する児童生徒の緊急時における心理状態に対応できるようにすると共に、他の児童とは同じ場では対応できにくいことに注意を払うようにする。 - SST(ソーシャルスキルトレーニング)で、社会生活や人間関係に適応する力を養う
- 子どもの特性を知るWISC-IV検査を実施し、一人ひとりの“得意”を伸ばす
- 高校卒業資格取得率98.9%※、単位取得へのフォローが手厚い
- 入学時は教室にも入れず、友達も作れずなかなか学校に行くことが出来なかった息子ですが先生方は子供に寄りそい、声をかけとても親身にやって下さいました。おそらくそれぞれのお子さんに合わせた指導をされていると思います。
- うちの息子はコミュニケーション能力が低く、高校生活を送れるか心配でしたがだんだんと先生方にも慣れ、本人のペースではありますがなんとか続けられました。先生方には特には厳しく、時には優しく、寄りそって下さり息子本人も親も興学社に来てよかったと感謝しておりま す。
- 私は中学校の時、いつもクラスで静かで誰とも話せませんでした。そんな時、興学社高等学院のことを知り入学してみると、先輩や先生方はとても優しく接してくださり、困ったことがあってもすぐに相談にのってくれるため、とても嬉しかったです。(後略)
- 最初は何も分からなくて、毎日、不安だらけでした。勉強も苦手で、友だち作りも苦手で…でも興学社高等学院の先生は、そんな苦手だらけの私にいつも優しく接してくれました。そして、少しずつ自分に自信が持てるようになりました。これからは、お母さんを助けていきたいです。
- 発達障がいのあるお子さんが自立するために
- 発達障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいのお子さんが不登校になってしまう原因とは?
- 境界知能とは?知的障がいとの違いや困りごと
- 知的障がいがあっても自立した一人暮らしは可能?
- 知的障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいの種類
- 発達障がいを抱えるお子さんの高校選びとは
- 発達障がいをもつ子どもの通信制高校の選び方
- 発達障がいがある子どもが高卒資格を目指すには
指導目標の設定
法律等で定められている教育の目的、学校の目的、学習指導要領に示されている各教科等の目標を前提とし、教育委員会の規則等に従い、地域や学校及び幼児児童生徒の実態に即した学校における指導目標を設定すると共に、幼児児童生徒の障害の状態に応じて、評価規準の調整、指導方法の変更、学習内容の調整、さらには指導目標・指導内容の個別設定を行う。
学習内容の変更・調整
一人一人の障害の状態に配慮し、学習内容の変更や、学習の量・時間の調整を行う。
情報保障
感覚と体験を総合的に活用した概念形成への配慮
一人一人の認知特性を把握し、それに応じた感覚と体験を総合的に活用できる学習活動を通じて、概念形成を促進するよう配慮を行う。
情報保障の配慮
一人一人の障害の状態に応じた情報保障を行うと共に、コミュニケーションの方法を検討するなど一人一人に適した配慮を行う。
認知の特性や身体の動き等に応じた教材の配慮
一人一人の認知特性、身体の動き等に応じた教材の配慮を行う。
ICTや補助用具等の活用
一人一人の障害の状態に応じて、ICTや補助用具等を活用し、学習の充実を図る。
学習機会や体験の意図的な確保
治療やリハビリテーションのため不足している学習や障害の特性から不足している体験などの機会を補うことができるよう、学習内容・活動を設定する。
心理面等について
他の子どもと比べ時間を要することへの配慮
障害の状態により、他の子どもと比べ時間を要することについては、本人の能力の発達を妨げないように、授業や試験について時間等の配慮を行う。
実施が困難な活動への補助や指導上の配慮
障害の状態により、実施が困難な活動についての活動内容・方法の工夫、指導上の配慮を行う。
予測できる学習活動の実施など学習に見通しが持てる配慮
学習予定を分かりやすい方法で知らせておくことや、それを確認できるようにすることで、心理的不安を取り除くと共に、その都度、状況を判断できるようにする。
人間関係の構築への配慮
集団におけるコミュニケーションについて配慮すると共に、他の子どもに対して障害特性等について理解を深めるような教育を行う。
心理状態・健康状態への配慮
障害の状態と健康状態により指導の内容・方法を柔軟に調整する。障害を起因とした不安感や孤独感を解消し、自尊心を高める配慮を行う。
自立と社会参加に必要な指導内容の設定
障害の状態や年齢を考慮しつつ、人間関係作り、学校、家庭、地域での役割作りに配慮する。卒業後の生活や進路を見据えて、一貫したキャリア教育の充実を図る。そのため、体験的活動や就業体験を充実させると共に、本人が自己選択・自己判断する機会を増やし、自分なりの生き方を考え、主体的に進路を選択できるようする。また、それぞれの発達の進んでいる側面を伸ばすことにより、自分の長所の自覚を促す。さらに、社会適応に必要な技術や態度が身に付くよう指導内容を工夫する。
共生の理念の涵養(かんよう)
それぞれの障害について、周囲の児童生徒や教職員が理解を深め、配慮や支援の環境作りを行う。また、障害の状態により集団活動への参加が難しい時には、集団を構成するメンバーで障害のある児童生徒の参加の方法を考える機会を設定する。さらに、障害のない児童生徒が支援する機会を設定する(教室移動、日常生活動作、学習活動、学級の係活動等)。
支援体制について
専門性のある指導体制の整備
校長がリーダーシップを発揮すると共に、学校全体として専門性の確保に努める。そのため、個別の教育支援計画、個別の指導計画を作成し、指導についての校内の教職員の共通理解を図り、学習の場面等を考慮した役割分担を行う。必要に応じ、学校内の資源(通級による指導、特別支援学級等)を活用したり、適切な人的配置(支援員等)を行う。
医療的ケアを行うための体制整備
医療的ケアを安全に行うことができるよう体制を整備する。
心理的負担を軽減できる学校・学級における配慮
障害のある子どもの不安等の心理的負担を軽減できるよう、全体の学習活動に支障のない範囲で学習環境の整備等を行う。
障害に対する児童生徒、教職員、保護者、地域の理解推進を図るための配慮
障害のある子どもについて、他の子どもの理解を推進する。必要に応じて、全員に、その障害特性などについて理解を深めるような教育を行う。教職員、保護者、地域に対しても理解増進を図るような活動を行う。
他の学校からの支援体制の整備
必要に応じ、特別支援学校のセンター的機能や他校の通級による指導、特別支援学級を活用するなど域内の教育資源を活用して支援体制を整備する(特別支援学校の施設・設備などの活用)。また、障害の状態により、小・中学校では困難な活動を特別支援学校でできるようにする(自立活動、作業学習など)。さらに、教育にかかわる学校のネットワークによるノウハウの共有を行う。
関係機関や外部専門家等との連携
教育センター等地域にある教育資源を最大限活用すると共に、医療、福祉、労働等の関係機関と連携する、あるいは、都道府県等の特別支援教育に係る専門家チームが校内委員会に助言するなどの配慮を行う。
緊急時の支援体制の整備
緊急時の対応について、人の動き、避難誘導、危機の予測、避難の方法、避難時の人的体制等、校内体制の確立のためのマニュアルを整備し、一人一人への対応を考える。また、緊急時の対応が十分にできるように避難訓練等に取り組む。
施設・設備について
校内環境のバリアフリー化
障害のある幼児児童生徒、教職員等が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、障害の状態や特性、個別のニーズに応じた環境にするために、スロープ、手すり、便所、出入口、エレベーター等の施設の整備計画時に配慮を行う。また、既存学校施設のバリアフリー化についても、障害のある幼児児童生徒の在籍状況等を踏まえ、所管する学校施設に関する合理的な整備計画を策定し、計画的にバリアフリー化を推進することが重要である。
発達、障害の状態及び特性等に応じた施設・設備の配慮
一人一人の幼児児童生徒の発達、障害の状態及び特性等に応じた指導内容・方法が十分に展開できるよう、自立活動等の学習指導を支援する様々な教育機器等の導入や施設整備を必要に応じて行う。また、幼児児童生徒が、それぞれの障害の認知特性、行動特性、感覚等に応じて、能力を最大限活用して自主的、自発的に学習や生活ができるよう、各教室等の施設・設備について、見えやすさ、分かりやすさなどに配慮を行う。
さらに、幼児児童生徒の学習及び生活の場として、日照、室温、音の影響等に配慮した良好な環境を確保するよう配慮を行う。特に、幼児児童生徒の障害の状態や特性等に配慮しつつ、その健康の保持増進に配慮した快適な空間とすることが重要である。
また、幼児児童生徒が心にゆとりをもって学校生活を送ることができ、他者との関わりの中で豊かな人間性を育成することができるよう、生活の場として快適な居場所を確保するよう心のケアを必要とする子どもへの配慮を行う。
災害等への対応に必要な施設・設備の配慮
地震等の災害発生時に障害の特性に応じた施設・設備を整備する。
※参照元:障害種別の学校における「合理的配慮」の観点(案)|文部科学省(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1314384.htm)
合理的配慮はわがままではない
合理的配慮を学校側に求めることに対して「先生に申し訳ない」や「自分の子だけ特別扱いされて申し訳ない」「わがままと言われそうで心配」といった感情を持つ保護者もいるようですが、合理的配慮は2016年4月に施行された「障害者差別解消法」という法に基づいた権利です。合理的配慮を求めることは決してわがままではなく、他のお子さんと同様に力を発揮しやすいようにするための工夫と捉えてください。
ただし配慮を提供する学校側にも人材や設備、資源の限界があるため、過度な負担とならないように合理的配慮の内容を両者で相談してすり合わせていく必要はあります。
合理的配慮をうまく受けるために
適切な合理的配慮を受けるには、提供する学校側にお子さんの特性を正確に伝えることが重要です。知的障がいや発達障がいの特性やレベルはひとり一人異なるため、支援して欲しい内容を学校関係者と話し合って決めていかないと学校側は適切な支援を行うことができないからです。
お子さんの合理的配慮については、保護者と教師だけでなく、スクールカウンセラーやお子さんの担当医師などの専門家の力を借りてつめていくことをおすすめします。
軽度知的障がい・発達障がいの
お子さんでも
通いやすい
「興学社高等学院」の魅力とは
軽度・中低度知的障がいやグレーゾーンの
お子さまも安心の学び場

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/)
大切なお子さんが軽度・中低度知的障がいや発達障がい、グレーゾーンであるとして診断を受けていると、今後の将来についてどうしても不安になってしまうでしょう。
しかし興学社高等学院では、障がいがない生徒に接するのと同様に、一人ひとりに共感して寄り添いながら、得意なことを好きなように学ぶことができる環境が整っています。
※参照元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/characteristics)令和2年度時点の実績
感覚を活かす実践型の授業で、自信を育てる

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
興学社高等学院のリベラルアーツ科では、視覚や聴覚などの「五感」を活かした体験型の授業が中心です。たとえば職業体験や実習を通じて、実際に体を動かしながら学ぶことで、机上の勉強が苦手なお子さんも「できた!」という達成感を得やすくなっています。
また、感覚の特性に配慮したカリキュラムや、行動の背景を理解して支援する「応用行動分析」の考え方も取り入れ、一人ひとりに合った学び方ができます。「わかる」「できる」を積み重ねることで、お子さんの自信と将来への希望が育ちます。
保護者・在校生の声

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
▼ 保護者の声 ▼
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/parents)
▼ 生徒の声 ▼
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/student)
▼ 千葉県の新松戸校はコチラ ▼
▼ 埼玉県の新越谷校はコチラ ▼
▼ 興学社高等学院のサポート内容や授業風景・口コミをもっと見るならコチラ ▼

興学社高等学院に通う生徒とその保護者、先生からそれぞれの口コミ評判を集めました。 実際に学校に関わっている人達だからからこそ出てくる生の声を、ぜひチェックしてみてください。