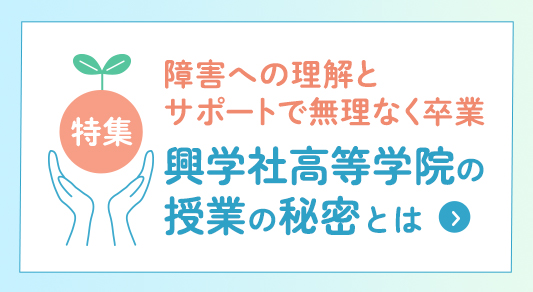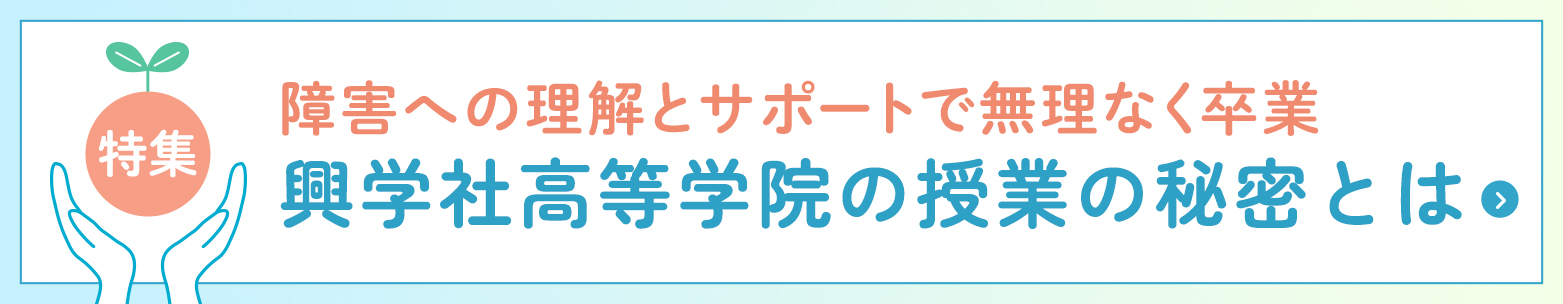知的障がいのあるお子さんの進路とは?
高校卒業後の進路に不安や悩みを抱える人は多いかと思います。進路の選択肢はお子さんの持つ特性やスキル、本人の希望によっても変わってくるでしょう。こちらでは、高校卒業後の進路や、働くために必要なスキルを養える福祉施設などを紹介していきます。
知的障がいを持つお子さんの進路の選択肢
進学
特別支援学校高等部や通信高校などを卒業した後の進路としては、就職したり福祉事業所へ通所するケースがほとんどです。しかし、高校卒業後に一般大学や専門学校へ進学する方も少数派ですが存在します。
進学先は一般大学や専門学校以外にも大学付属などの「知的障がい者のための福祉型専攻科」への進学、という道もあります。福祉型専攻科を設置する大学は全国的に10校程度しかありませんが、青年期の移行支援教育として学習や社会参加などのスキルを学ぶことができます。
就職
特別支援学校高等部や高校卒業後に直接企業などへ就職するケースです。一般企業の場合、障がいの有無に関係なく就職する「一般就労」と、障がい者のために設けられた「障がい者雇用枠」という2つの選択肢があります。
障がい者雇用枠は障がい者雇用促進法で定められた障がい者のための枠で、職務内容や労働時間が配慮されているため一般枠と比べると働きやすい環境となります。ただし、その分給与は一般枠よりも低くなりがちです。
馴染める職場を選ぶためにも、自身の特性にはどちらの雇用体制が合っているか、どのような職種が適切なのかなど周囲と相談しながら決めることが重要です。
特例子会社
特定子会社とは、障がいがある方の雇用促進と雇用の安定性を図るために設置された子会社のことです。障がい者の雇用に特化していることが特徴で、業務内容や仕事の進め方、雇用時間など障がい者の特性を配慮した職場環境が整っています。
一般企業においても「障がい者雇用」という枠が義務付けられており、業務内容や雇用条件に配慮がされています。この「障がい者雇用」と「特定子会社」は何が違うかというと、特定子会社は勤務管理や体調管理などが行き届いている点です。一般企業の場合は非障がい者の割合が高いため、各社員のサポートが十分に得られない可能性がありますが、特定子会社は障がいのある方を雇用する会社のため、勤務体制や健康・体調管理が手厚く、何かあった際の相談役の設置もされています。
また設備面でも、障がいのある方のために設立された施設のためバリアフリー対応などが整っています。
就労支援施設への通所
就労支援施設とは、障がいがある方の働く場所を確保して働くための知識や能力を向上させるための施設のことです。高校を卒業して進学や就職がすぐにできない場合、このような施設利用することができます。身体障がいや知的障がい、発達障がい、難病の方などを対象としており、医師の診断書や自治体が判断すれば障がい者手帳がなくても利用できます。
就労支援施設には「就労継続支援事業」A型とB型、「就労移行支援」「就労定着支援」というサポートがあります。こちらでは、それぞれの概要や利用対象者などを紹介していきます。
就労移行支援
就労移行支援とは、障がいを抱える方に対して就労するために必要な知識や技術を習得してもらい、就労できるようにサポートする施設です。日本全国に約3,000カ所以上あり、社会福祉法人や民間企業、NPO法人などが運営しています。
※参照元:厚生労働省「地域における就労移行支援及び就労定着支援の動向及び就労定着に係る支援の実態把握に関する調査研究」(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001113436.pdf)
利用対象者
- 一般就労したいと考えている方
- 18歳以上65歳未満の方(要件を満たせば65歳以上も可)
- 精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
- 難病等のある方
給与
就労移行支援事業所では、基本的に給与の支払いはありません。プログラムの一環として実習などを行うこともありますが、これは訓練としての仮の業務だからです。事業所によっては給料が発生する業務に就くこともありますが、雇用契約を結ぶわけではないため最低賃金よりも低い給与となります。
期間
就労移行支援事業所を利用できる期間は原則2年となっています。
仕事内容
ひとり一人の利用者に合わせた支援計画を提供してくれます。連携している企業に職場見学へ行ったり実習を経験することもあります。就職に向けた面接の方法や履歴書の書き方など教えてくれたり、就職後も継続して支援してくれます。
就労継続支援A型
就労継続支援事業所A型は、一般企業などで働くことは困難であっても、一定の支援があれば雇用契約を結んで働くことのできる方を対象にしたサービスです。
就労の機会と生産活動など、働くために必要な知識とスキル向上の訓練などを行います。利用者と事業所の間に雇用契約があるため、賃金を得られるのが特徴です。
就労継続支援A型事業所は日本全国に約4,415カ所(令和5年)あり、社会福祉法人や民間企業、NPO法人などが運営しています。
※参照元:厚生労働省「就労継続支援A型に係る報酬・基準について≪論点等≫」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001155197.pdf)
利用対象者
- 18歳から65歳未満の障がい者を抱える人
- 就労移行支援事業では就労に結びつかなかった人
- 特別支援学校を卒業後企業での雇用に結びつかなかった人など
給与
就労継続支援事業所A型の場合、雇用契約が発生するため利用者に作業工賃が支払われます。令和3年度の利用者1人当たりの平均賃金月額は81,645円、時給に換算すると926円という実績もあります。
※参照元:厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001042285.pdf)
期間
事業所との間に特に利用期限はないため、長期に渡り利用できます。
仕事内容
事業所では利用者のスキルに合わせさまざまな業務を用意しています。例をあげると次のような職業があります。
- パソコンの操作などを用いた事務作業
- 商品管理の業務
- パーツ組み立てや加工
- 農作業
- 清掃作業
- 食品など製造業の加工など
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、A型と同様に一般企業への就労が難しい障がい者に対しての就労支援サービスで、就労の機会や就労に必要な知識やスキル向上に必要な訓練などを行います。
就労継続支援A型と異なる点は「雇用契約を結ぶかどうか」という点です。A型は事業所と労働基準法に則った雇用契約を結びますが、B型は結びません。工賃は低いものの、利用者の抱える個別の特性に合う作業内容と短い作業時間という条件があったり、職員のサポートなどがあるため和気あいあいとした雰囲気の事業所が多いようです。
利用対象者
就労継続支援B型を利用できるのは、障がいを抱える方や難病のある方で下記のいずれかに該当する方となります。
- 就労経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇用されることが困難になった方
- 50歳以上の方、または障がい基礎年金1級を受給している方
- 就労移行支援事業者などによるアセスメントにより、就労面の課題が把握がおこなわれていて、かつ就労継続支援B型事業所を利用するほうが適切だと判断された方
※参照元:厚生労働省「障がい福祉に関する制度沿革・概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000675281.pdf)
給与
就労継続支援B型では作業に給与が発生しますが、雇用契約はないので最低賃金は保障されません。令和3年度のB型事業所の平均時給は233円、平均月給は16,507円でした。
※参照元:厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001042285.pdf)
期間
事業所との間に特に利用期限はないため、長期に渡り利用できます。
仕事内容
利用者の個別性や障がい特性に合わせた作業内容、作業時間となり、就労継続支援A型よりもさらに簡単な業務内容となります。職員に見守られながらの軽作業や単純作業、清掃作業などが多いようです。
その他の支援施設
これまで紹介した支援施設以外にも知的障がいを抱える方を対象にした福祉サービスがあります。サービスの形態は複数に分かれますが、働くことを目標にする場合は「訓練等給付の自立訓練」という福祉施設を利用できます。
自立訓練の施設では、生活能力や身体能力を高めるための訓練や、働くためのステップとして簡単な作業やソーシャルスキル向上の訓練などを学ぶことが可能です。
自立訓練には通所型と宿泊型があり、通所型は自宅などから施設は通います。宿泊型の自立訓練事業所の場合は、一般就労やほかの障がい福祉サービスを日中に利用している方を対象にして、夜間に居住できる場所として提供されます。
働くのが困難な方には「介護型」の福祉支援サービスもあります。
自立訓練(生活訓練)とは
自立訓練は、障害者総合支援法に定められた「指定障がい福祉サービス」のひとつです。障がいの特性を持つ方が自立した生活が送れるように訓練したり支援を行います。
自立訓練は2種類あり、身体機能のリハビリをおこなう「機能訓練」と、日常生活を自分の力でできるよう訓練する「生活訓練」の2種類があります。生活訓練は生活リズムを整えるような基本的な内容から体調管理、お金の管理、買い物、公共交通機関の乗り方、コニュニケ―ションスキルの向上を目指すなど多岐に渡ります。
自立訓練事業所の種類
自立訓練の事業所には大きく分けて3つのタイプがあります。
- 事業所に通う通所型:
通所してスキルアップする訓練を行う事業所タイプです。午前から夕方まで訓練を行うことが一般的ですが、体調や家庭の事情によっては通所時間の変更にも柔軟に対応してくれます。毎日通所することで生活リズムの改善などにもつながります。 - 自宅で支援を受ける訪問型:
支援者が利用者の自宅に訪問して訓練を行うタイプです。事業所に通所することが身体的や精神的に困難な方に対して実施されます。通所と訪問を併用することもできます。 - 事業所に泊まる宿泊型:
夜間や休日などに事業所に宿泊しながら訓練や支援を受けるタイプの事業所です。日常生活に必要なスキルを訓練するだけでなく、宿泊を通して他の利用者との共同生活ができる貴重な経験になります。
対象者・利用期間
自立訓練事業所を利用できる対象者は、「地域生活を営む上で一定の支援が必要な方」です。
他にも次のような利用条件があります。
- 65歳未満の方
- 精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
- 障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方
- 市区町村の自治体から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方
また、利用期間は原則最長24カ月です。市区町村に申請して審査に通れば24カ月を超える訓練が認められるケースもあります。
支援の内容
自立訓練は障害のある方が自立した生活ができるようにするため、生活能力の維持・向上を目指していく内容になります。障がいの特性や個々のおかれた状況などによって「自立」の定義は異なります。事業所の相談員は、そういったひとり一人の状況をカウンセリングなどを設けて話し合いながら、適切な支援やカリキュラムを提供してくれます。
内容は大きく分けて下記のようなものになります。
- 生活の基礎をつくることを目指す(食生活や生活リズム、健康管理など)
- 金銭管理や家事、買い物、公共機関の利用など生活できる能力を身に付ける
- 人間関係やコミュニケーションスキルの向上を目指す
- 就労を目指したり、恋愛や趣味など生活の充実を目指す
まとめ
卒業後の進路選びは、まずは進学か就職かを選ぶことから始めてください。そして就職を選択するのであれば、卒業後にすぐに就職するか、仕事に就くためのスキル向上をしてから求職を目指すのか、本人の特性とサポートしてくれている周囲の人達と相談しながら決めることが重要です。
厚生労働省により定められた障がい者総合支援法にはさまざまな支援サービスがあります。周囲と相談しながらエリアの福祉支援サービス施設を上手に利用しましょう。
軽度知的障がい・発達障がいの
お子さんでも
通いやすい
「興学社高等学院」の魅力とは
軽度・中低度知的障がいやグレーゾーンの
お子さまも安心の学び場

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/)
大切なお子さんが軽度・中低度知的障がいや発達障がい、グレーゾーンであるとして診断を受けていると、今後の将来についてどうしても不安になってしまうでしょう。
しかし興学社高等学院では、障がいがない生徒に接するのと同様に、一人ひとりに共感して寄り添いながら、得意なことを好きなように学ぶことができる環境が整っています。
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)で、社会生活や人間関係に適応する力を養う
- 子どもの特性を知るWISC-IV検査を実施し、一人ひとりの“得意”を伸ばす
- 高校卒業資格取得率98.9%※、単位取得へのフォローが手厚い
※参照元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/characteristics)令和2年度時点の実績
感覚を活かす実践型の授業で、自信を育てる

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
興学社高等学院のリベラルアーツ科では、視覚や聴覚などの「五感」を活かした体験型の授業が中心です。たとえば職業体験や実習を通じて、実際に体を動かしながら学ぶことで、机上の勉強が苦手なお子さんも「できた!」という達成感を得やすくなっています。
また、感覚の特性に配慮したカリキュラムや、行動の背景を理解して支援する「応用行動分析」の考え方も取り入れ、一人ひとりに合った学び方ができます。「わかる」「できる」を積み重ねることで、お子さんの自信と将来への希望が育ちます。
保護者・在校生の声

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
▼ 保護者の声 ▼
- 入学時は教室にも入れず、友達も作れずなかなか学校に行くことが出来なかった息子ですが先生方は子供に寄りそい、声をかけとても親身にやって下さいました。おそらくそれぞれのお子さんに合わせた指導をされていると思います。
- うちの息子はコミュニケーション能力が低く、高校生活を送れるか心配でしたがだんだんと先生方にも慣れ、本人のペースではありますがなんとか続けられました。先生方には特には厳しく、時には優しく、寄りそって下さり息子本人も親も興学社に来てよかったと感謝しておりま す。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/parents)
▼ 生徒の声 ▼
- 私は中学校の時、いつもクラスで静かで誰とも話せませんでした。そんな時、興学社高等学院のことを知り入学してみると、先輩や先生方はとても優しく接してくださり、困ったことがあってもすぐに相談にのってくれるため、とても嬉しかったです。(後略)
- 最初は何も分からなくて、毎日、不安だらけでした。勉強も苦手で、友だち作りも苦手で…でも興学社高等学院の先生は、そんな苦手だらけの私にいつも優しく接してくれました。そして、少しずつ自分に自信が持てるようになりました。これからは、お母さんを助けていきたいです。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/student)
▼ 千葉県の新松戸校はコチラ ▼
▼ 埼玉県の新越谷校はコチラ ▼
▼ 興学社高等学院のサポート内容や授業風景・口コミをもっと見るならコチラ ▼
- 発達障がいのあるお子さんが自立するために
- 発達障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいのお子さんが不登校になってしまう原因とは?
- 境界知能とは?知的障がいとの違いや困りごと
- 知的障がいがあっても自立した一人暮らしは可能?
- 知的障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいの種類
- 発達障がいを抱えるお子さんの高校選びとは
- 発達障がいをもつ子どもの通信制高校の選び方
- 発達障がいがある子どもが高卒資格を目指すには

興学社高等学院に通う生徒とその保護者、先生からそれぞれの口コミ評判を集めました。 実際に学校に関わっている人達だからからこそ出てくる生の声を、ぜひチェックしてみてください。