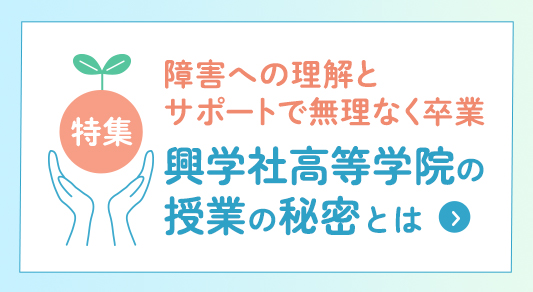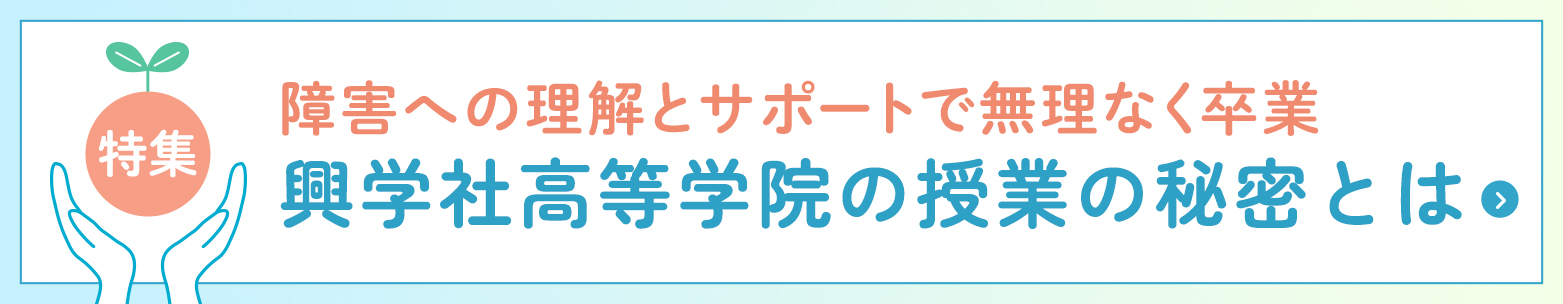発達障がいをもつ子どもの通信制高校の選び方
将来への準備と充実した高校生活を送るためには、発達障がいへの理解が深く、特性に合わせた環境やサポートが充実している学校を選ぶ必要があります。ここでは、発達障がいに適した通信制高校を選ぶ時のポイントを紹介しています。
学習面の個別サポートが
しっかりしているか
発達に特性がある場合、集団授業で使う一般的な教材や講師に合わせた授業ペースへの対応が難しいことがほとんどです。学習の進め方や理解度など個人の学習レベルに合わせた指導をおこなっている学校だと、周囲に遠慮することなく自分のペースで学習を進められ、モチベーションアップにも繋がります。
また、個別サポートが行き届いていると、学習の取り組み方や普段の様子など、担任と保護者で情報共有もしやすくなり、より寄り添ったサポートがしやすくなります。
心理面の個別サポートが
しっかりしているか
発達障がいというのは人によって程度が異なり、また見た目でわかるようなものではありません。ですから、何気ない行動で知らずに傷つけたり、ひどい場合はいじめに発展することも。そうした理解がない環境での精神的な負担は計り知れません。
特性に合わない環境はマイナスにしかなりませんので、充実した高校生活を送るなら発達障がいへの理解とサポート体制を用意している学校を選ぶのが得策です。心理士の資格やカウンセラーの資格など、専門の資格を持った教員が常勤している学校を選ぶと、精神面の負担を軽減することができます。
生徒同士のコミュニケーションサポートをしているか
集団行動や人間関係などコミュニケーションに苦手意識を持つ生徒は少なくありません。社会に出てからは円滑なコミュニケーションが求められるため、高校で生徒同士のコミュニケーションに慣れておくことは大切です。
一度打ち解けてしまえば積極的にコミュニケーションを取れるようになるので、最初の一歩をどのようにサポートしているかをチェックしましょう。
「修学旅行」「文化祭」「スクーリング」などの行事を通してコミュニケーションの場を設けている学校もあります。また、通信制高校では、生徒数や生徒同士の交流の場が少ないため、先生が生徒に積極的なコミュニケーションを取ってくれるかどうかも確認しておきたいポイントです。
専門課程の授業で
個性を伸ばしてくれるか
発達障がいでは、記憶力や集中力が人より秀でているなど、ある種の才能を持っている子が少なくありません。そうした個性を探ることは将来への道にもなりますので、 さまざまな専門課程を用意している高校を選ぶといいでしょう。
発達障がいでも専門知識や技能を身につけることはできないことではなく、資格取得や仕事に繋がるなど自立するための大きな武器になります。興味のある授業を無理なく受けられる学校だと、未来への可能性が広がります。
常駐カウンセラーによるサポートがあるか
学校内で心のケアを行っているのがスクールカウンセラーです。集団生活をする教育施設ですが、閉鎖的な場所でもあるため、そこに関わる人の精神的負担を軽くする役割があります。カウンセリングの対象は、生徒だけではありません。教師の心のケアや保護者との面談も仕事の範囲です。
発達障がいを抱えているからとは限りませんが、学校生活では本人にとってショッキングなことが起こる可能性があります。自信を失うことがあるかもしれません。
そんな時、メンタル面での支えが必要です。そのため、通信制高校を選ぶ際は、常駐のカウンセラーが在籍し、生徒が悩みやストレスを抱え込まないようにサポートしてくれる体制が整っているかを確認してください。保護者へのサポート体制もチェックしたいところです。
ソーシャルワーカーによるサポートがあるか
スクールソーシャルワーカーは、生徒を取り巻く環境や関係機関との連携や調整を通して、一人ひとりの生活の質を向上することが役割です。カウンセラーが心の問題を解決するのに対して、ソーシャルワーカーは地域社会や関係機関、家庭などと連携をとって環境の課題を解決します。スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが互いに協力しながらそれぞれの役割を分担して課題解決に取り組む体制が大切です。
通信制高校でも、ソーシャルワーカーによるサポートは確認したいことのひとつ。いじめや不登校などの問題は、心のサポートだけでは解決しません。安心して学ぶ環境を整えるためにも、ソーシャルワーカーの在籍の有無を確認しておきましょう。
SST(ソーシャルスキルトレーニング)の授業を行っているか
SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは
ソーシャルスキルとは、社会の中で様々な人と良好な関係を築くスキルのことです。協力しながら仕事をしたり、適切な距離感を保ったり、自分も相手も心地よく過ごすためのスキルのため、人と関わる上で必須とされています。
成長過程で自然と身につける人が多いスキルですが、発達障がいはこのソーシャルスキルの習得に困難を抱えている特性が顕著です。学生のうちに訓練を通して、ソーシャルスキルを身につけておくことが、社会に出てからの生きやすさにつながります。
ソーシャルスキルのトレーニングで学ぶのは、いわゆる「常識」とされている行動パターンです。ある場面において、「こうしたほうがいい」あるいは「これはしないほうがいい」といった暗黙のルールをパターンとして学びます。
SSTに期待できること
成長過程でソーシャルスキルを身につけられなかった人は、不適切な行動をとってしまい、相手を怒らせたり、集団を乱したりしてしまいます。そんなことが積み重なれば、社会生活に困難を抱えてしまうことも少なくありません。SSTで期待されている行動を学ぶことで、こうした困難を軽減できます。
仕事や家事を順序だてて行うことが難しい場合も、ソーシャルスキルを鍛えることでその困難さを減らすことが期待できます。
SSTでは、他者との関係構築をスムーズにして、場に馴染み、効率的に仕事を行うにはどうすればよいかを身につけることが目標です。
SSTはどのように行われる?
ゲーム、遊び
ゲームや遊びには、一定のルールがあります。場合によっては、仲間との相談も必要です。ゲームであれば、勝ち負けの結果を受け入れるという訓練にもなります。ゲーム感覚での訓練は、心理的なハードルが低く、取り組みやすいSSTです。
ロールプレイ
特定の場面を設定して、その場面においてどのような行動をとるべきかを学びます。本人や参加者が交替で役割を演じることで、人の行動がからの学びも得られるのが特徴です。自分で実際に行動して、行動パターンを体で覚えていきます。
ディスカッション、ディベート
一つのテーマについて、複数人で話し合うことを通じて、他人の考え方を知り、適切なふるまいを学ぶのがディスカッションやディベートを通したSSTです。ディスカッションにおいては、問題を抱えた人だけを変えようとするのではなく、環境の調整という観点でも有効とされています。
ソーシャルストーリー
自閉症スペクトラムの子どもの教育にかかわってきたキャロル・グレイが考案したSST。絵やテキストを使用してソーシャルスキルを学びます。自分の意志をで言葉や行動を選ぶために、理解力を高める訓練です。
共同行動
目標や目的達成のために、他人と相談しながら役割分担を決め、助け合う訓練です。実践的に共同行動を行うことで、社会生活のスキルを身につけます。
日常的な行動
日常の中でもSSTは実施できます。基本は挨拶。良好な人間関係を作るための基本的なスキルです。どのような場面でどのような挨拶をするといいのかを学び、自然な挨拶ができるようになります。また、相手の気持ちを表情や態度から察するために、様々なシチュエーションを通して、自分がどう感じるかを体験することも大切な訓練です。日常の中には、雑談のような人との関係を良好にするために必要な会話があります。日頃の会話を通して、コミュニケーションスキルを養うこともSSTのひとつです。
興学社高等学院なら安心
興学社高等学院では、入学時にWISC-Ⅳ(ウィスク・フォー)検査をおこない、その 分析結果に基づいた指導を個別でおこなっています。しかも、授業は必修授業の他、興味のある分野から選択することができるなど個性を探り伸ばす授業体制です。
また、療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)や精神保健福祉手帳(あおの手帳)の有無に問わずに入学可能。 何かしらの困難を抱えている生徒を迎え入れ、十分に考慮した指導と学校生活を提供しています。
障がいへの理解とサポートで
無理なく卒業できる
興学社高等学院の特徴とは
軽度知的障がい・発達障がいの
お子さんでも
通いやすい
「興学社高等学院」の魅力とは
軽度・中低度知的障がいやグレーゾーンの
お子さまも安心の学び場

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/)
大切なお子さんが軽度・中低度知的障がいや発達障がい、グレーゾーンであるとして診断を受けていると、今後の将来についてどうしても不安になってしまうでしょう。
しかし興学社高等学院では、障がいがない生徒に接するのと同様に、一人ひとりに共感して寄り添いながら、得意なことを好きなように学ぶことができる環境が整っています。
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)で、社会生活や人間関係に適応する力を養う
- 子どもの特性を知るWISC-IV検査を実施し、一人ひとりの“得意”を伸ばす
- 高校卒業資格取得率98.9%※、単位取得へのフォローが手厚い
※参照元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/characteristics)令和2年度時点の実績
感覚を活かす実践型の授業で、自信を育てる

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
興学社高等学院のリベラルアーツ科では、視覚や聴覚などの「五感」を活かした体験型の授業が中心です。たとえば職業体験や実習を通じて、実際に体を動かしながら学ぶことで、机上の勉強が苦手なお子さんも「できた!」という達成感を得やすくなっています。
また、感覚の特性に配慮したカリキュラムや、行動の背景を理解して支援する「応用行動分析」の考え方も取り入れ、一人ひとりに合った学び方ができます。「わかる」「できる」を積み重ねることで、お子さんの自信と将来への希望が育ちます。
保護者・在校生の声

※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/school_life/timetable)
▼ 保護者の声 ▼
- 入学時は教室にも入れず、友達も作れずなかなか学校に行くことが出来なかった息子ですが先生方は子供に寄りそい、声をかけとても親身にやって下さいました。おそらくそれぞれのお子さんに合わせた指導をされていると思います。
- うちの息子はコミュニケーション能力が低く、高校生活を送れるか心配でしたがだんだんと先生方にも慣れ、本人のペースではありますがなんとか続けられました。先生方には特には厳しく、時には優しく、寄りそって下さり息子本人も親も興学社に来てよかったと感謝しておりま す。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/parents)
▼ 生徒の声 ▼
- 私は中学校の時、いつもクラスで静かで誰とも話せませんでした。そんな時、興学社高等学院のことを知り入学してみると、先輩や先生方はとても優しく接してくださり、困ったことがあってもすぐに相談にのってくれるため、とても嬉しかったです。(後略)
- 最初は何も分からなくて、毎日、不安だらけでした。勉強も苦手で、友だち作りも苦手で…でも興学社高等学院の先生は、そんな苦手だらけの私にいつも優しく接してくれました。そして、少しずつ自分に自信が持てるようになりました。これからは、お母さんを助けていきたいです。
※引用元:興学社高等学院 新松戸校公式HP(https://highschool.kohgakusha.com/about/student)
▼ 千葉県の新松戸校はコチラ ▼
▼ 埼玉県の新越谷校はコチラ ▼
▼ 興学社高等学院のサポート内容や授業風景・口コミをもっと見るならコチラ ▼
- 発達障がいのあるお子さんが自立するために
- 発達障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいのお子さんが不登校になってしまう原因とは?
- 境界知能とは?知的障がいとの違いや困りごと
- 知的障がいがあっても自立した一人暮らしは可能?
- 知的障がいのお子さんへの接し方とは?
- 発達障がいの種類
- 発達障がいを抱えるお子さんの高校選びとは
- 発達障がいがある子どもが高卒資格を目指すには
- 発達障がいを抱えるお子さんの高校卒業後の進路とは?

興学社高等学院に通う生徒とその保護者、先生からそれぞれの口コミ評判を集めました。 実際に学校に関わっている人達だからからこそ出てくる生の声を、ぜひチェックしてみてください。